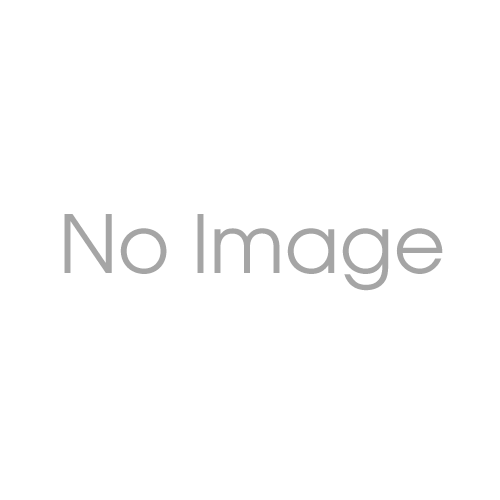私たちの交通システムは、急速にデジタル化と自動化が進む中で、次世代のインフラ整備と新たな技術の導入が不可欠になっています。2024年の各種セッションでは、日本や中国での交通システム改革の最前線を担うETC2.0技術、自律走行の進展、インテリジェント交通(ITS)の実現について多角的に議論され、デジタル技術がもたらす未来のモビリティの姿が浮き彫りになりました。以下では、ETCシステムの意義、インフラのデジタルトランスフォーメーション、持続可能な未来へのビジョンについてまとめます。
まず、日本のETC2.0システムが注目を集めた理由についてです。ETC(電子料金収受システム)は、もともと通行料金のスムーズな収受を目的に導入されましたが、現在では交通データの収集とリアルタイムの運用管理に役立っています。日本では、ETC普及率が約95%に達し、さらにETC2.0により道路渋滞の解消、安全性の向上、災害時の無料通行などさまざまな利点が強調されました。一方で、システムの維持・管理にかかるコストや、ETC機器の高コストによる導入の障壁も指摘されており、課題解決に向けた持続可能な戦略が求められています。
さらに、このセッションで議論されたもう一つの重要なテーマは、中国との技術的な比較と連携です。中国はETCシステムにおいて、データ管理と運用効率に力を入れており、公共交通サービスに無料で情報提供を行うなど、異なるアプローチでの展開を進めています。両国のアプローチの比較から、ETC2.0の技術的な応用やデジタル道路インフラの設計におけるベストプラクティスが見い出され、相互のシステム改善に向けた重要な視点が得られました。
そして、今後の持続可能なモビリティの基盤として、ETC2.0やITSの役割が拡大する中、データの利活用が鍵を握ることも明らかにされました。ETCでは、センサーやビッグデータ解析を駆使し、道路上の危険エリアを特定し、事故の予防策を講じることが可能です。また、車両やインフラがネットワーク化されることで、リアルタイムの渋滞解消や事故防止が実現し、道路の安全性が飛躍的に向上することが期待されています。さらに、高齢化が進む中で、自動運転技術の導入によってドライバー不足問題にも対応可能となり、地域社会全体が恩恵を受けることが見込まれています。
2024年の会議を通じて見えてきたのは、未来の交通システムがETCや自律走行技術を軸に、大きなデジタル変革を迎えているということです。日本と中国がそれぞれのインフラ整備において相互に学びながら、インテリジェント交通(ITS)とデジタルインフラのさらなる発展を図ることは、今後のモビリティの未来を支える重要な要素となるでしょう。